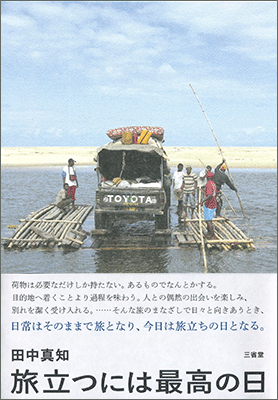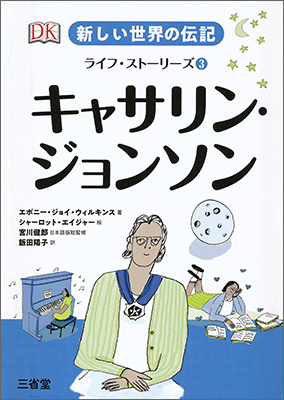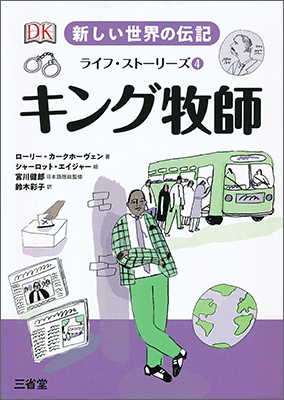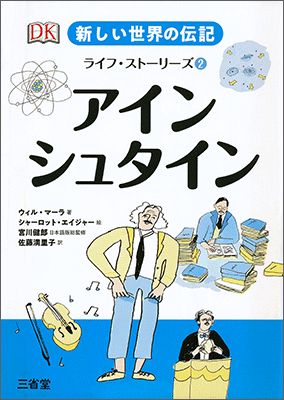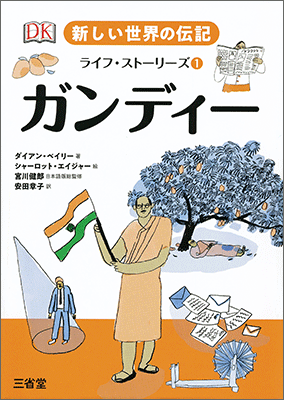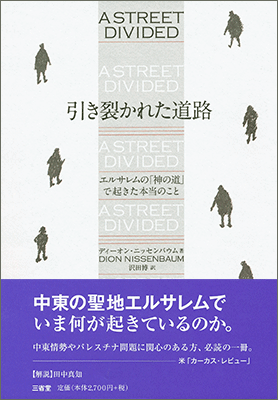引き裂かれた道路 エルサレムの「神の道」で起きた本当のこと
- 一般
- 著者名
- ディーオン・ニッセンバウム 著/沢田 博 訳
- 判型
- 四六
- ページ数
- 376頁
- ISBN
- 978-4-385-36061-4
中東の聖地エルサレムの「神の道」と呼ばれる通りには,イスラム教徒とユダヤ教徒が通りを挟んで住んでいる。「パレスチナ問題」を日々の現実として生きる無名の人々の姿を,実際にこの地に住み,直接取材をしたアメリカ人ジャーナリストが描く。
目次
第1章 無人地帯
第2章 牡牛の父、あるいは裏切りの地
第3章 殉教者たち
第4章 入植者たち
第5章 協力者
第6章 平和主義者たち
第7章 よきアラブ人
第8章 再びの分割を目指す人々
エピローグ 「アブトルの包囲」
本書関連年表
日本語版解説 田中真知
原注/参考文献
★著者・訳者略歴
はじめに
この物語ではエルサレムの真実を伝える。そこには愛もあれば戦争もあり、難民の発生があり、欺瞞があり裏切りもある。
そこでは、どんなささいなことでも争いの種となる。
「日本語版解説」田中真知(作家)
三大宗教の聖地──それはエルサレムをあらわすのに、しばしば用いられる言い回しだ。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という、同じ神と契約を結んだ三つの一神教にとってエルサレムは等しく特別な場所である。だから、この言い方はまちがいではない。そこから浮かんでくるのはエルサレムという一つの聖地を三つの宗教が分かち合っているようなイメージだ。
しかし、実際にエルサレムの街を歩きまわっていると、そのような印象はだんだん薄れてくるかもしれない。むしろ、ここには三つの異なるエルサレムが同じ空間を占めながら、レイヤーのように重なりあって存在しているといったほうがいいかもしれない。
最初にそれを感じたのは、陸路でヨルダンからイスラエル側に入り、エルサレム行きのバスを探していたときのことだった。停車していたミニバスに乗っていたパレスチナ人らしき家族連れに、「このバスはエルサレムに行きますか」とたずねた。
すると父親らしき人は指を立てて首をふり「エルサレムには行きません。アル・クドゥスには行きますけど」といって、かすかに笑った。その意味するところに一瞬遅れて気づき、私も笑った。ムスリム(イスラム教徒)の間ではエルサレムは中世以来、アル・クドゥス(アラビア語で「聖なるもの」)という名で呼ばれてきた。バスの行き先は同じであっても、ムスリムがそこに見ている風景と、ユダヤ教徒やキリスト教徒が見ている風景とでは、おそらくまるでちがっている。
地図を見ても、そのことがわかる。観光案内所でくれる地図には聖地の中心を占める丘は「神殿の丘」と書かれている。これはユダヤ教徒にとってその下に古代のユダヤ神殿が埋まっている場所であることに由来する。しかし、ムスリムはこの丘をハラム・アッシャリフ(高貴な聖域)と呼び、預言者ムハンマドの昇天した場所と見る。地理的には同じ場所であっても、心理的には両者は重ならない。
宗教や民族が同じだからといって一枚岩というわけではない。宗派やコミュニティや政治的立場のちがいが、レイヤーをいっそう複雑にしている。パレスチナ人といってもムスリムだけではなく、キリスト教徒もいれば、イスラエル国籍を持つ者もいる。また、エルサレムは最大の聖地だけにキリスト教のあらゆる宗派が集結しているが、互いの仲はあまり良くない。たびたび新聞ネタになる聖墳墓教会での縄張り争いもそうだ。
聖墳墓教会はイエスが殺され、復活した場所につくられたキリスト教徒にとっては最重要の巡礼地だ。その管理は歴史的な経緯によって、七割をギリシア正教会が、残り三割をアルメニア正教会、ローマカトリック教会、シリア正教会、コプト正教会、エチオピア正教会が受け持つことになっている。それぞれの宗派ごとに、どの派が、いつ、どこを掃除するか、どの順番で礼拝するかなどが細かく決められているのである。
しかし、この取り決めをめぐって各宗派の聖職者同士は恒常的に緊張関係にあり、なにかのきっかけで乱闘騒ぎになることも少なくない。ギリシア正教会の僧が式典のときに、カトリックが管轄する聖堂に足を踏み入れたとか、アルメニア正教会の式典の方法がギリシア正教会にとって納得できないとか、掃除のときゴミを自分の管轄する敷地に掃きだしたといったことをきっかけに聖職者同士が殴り合いをはじめ、逮捕者が出たこともある。
ユダヤ教徒についても、その立場はじつにさまざまである。イスラエルのユダヤ人口の一割ほどを占めるハレーディーと呼ばれる超正統派ユダヤ教徒は働くことなく国からの補助金で生活している特別な階級であり、納税も兵役も免除されてきた(ただし2017年からハレーディーについても兵役が義務化された)。彼らの中でもとくに過激な一派は、神の意志を待たずに人為的につくられたイスラエルという国家もシオニズムも認めない。
超正統派ほど極端ではないが、聖書をよりどころに日常生活のあらゆる側面を取り決め、入植活動に熱心なのが宗教右派。宗教熱心だが穏健な正統派。その他の約七割を占めるのは、そこまで宗教熱心ではない伝統派や世俗派である。
さらにユダヤ教徒といっても、その出自によって東欧系のアシュケナジーム、スペイン系のスファラディム、北アフリカや中東出身のオリエント系、少数派のエチオピア系などがいる。エチオピア系はユダヤ教徒でありながらイスラエルのユダヤ社会の最底辺をなし、社会的な差別に対して抗議行動を起こしたこともある。同じユダヤ教徒でも、宗派、民族、階級などによって、それぞれちがうレイヤーを生きているのである。
ただ、問題は異なるレイヤーがたくさん存在していることではなく、そのレイヤー同士が対話するための回路が失われていることにある。その決定的なきっかけが1948年のイスラエル国家の建国にあったことはいうまでもない。
強引な建国に反対したアラブ諸国は連合してイスラエルに宣戦布告し、第一次中東戦争がはじまる。結果はイスラエルの勝利で100万ともいわれるアラブ人(のちのパレスチナ人)が難民となった。このときヨルダンとイスラエル両軍の代表によって、エルサレムを東西に分断する二本の境界線が引かれ、その間には鉄条網で隔てられたどちらにも属さない狭い無人地帯ができた。1967年の第三次中東戦争によってイスラエルはヨルダン川西岸や東エルサレムを占領し、19年にわたって東西を隔てていた鉄条網は撤去され、無人地帯には「アサエル通り」という名前がつけられた。
本書は、この無人地帯の一部、のちのアサエル通りをはさんで両側に暮らした人たちの交流や葛藤のドラマを描いている。ユダヤ人、パレスチナ人というだけで一括りにされがちな人びとが、それぞれに多様な立場や視点の中で日々混乱や迷いや矛盾を抱えながら生きている姿がリアルに伝わってくる。矛盾の根底にはいうまでもなくイスラエルのパレスチナ人に対する差別的な扱いがある。
1993年のオスロ合意によって、ガザとヨルダン川西岸におけるパレスチナ人の暫定自治が認められたものの、パレスチナ難民問題、エルサレムの帰属権、ユダヤ人入植地といった問題は先送りされ、イスラエルはユダヤ人国家というアイデンティティーを確たるものにするための政策を進めていく。本書でもふれられているように、土地開発計画、建築許可、選挙権、教育や水問題など暮らしをめぐるさまざまな権利はイスラエル政府によって握られ、それを拒む権利を与えられていないパレスチナ人は暴力によって抵抗しつづけてきた。自爆テロのような破滅的な手段で立ち向かうパレスチナに対し、イスラエルはガザ地区への空爆を行い、ヨルダン川西岸地区を囲むように分離壁の建設を進めている。
しかし、本書はこのようなイスラエルの強権的なやり方に対して、パレスチナ人の苦悩や窮状を報告し、あるべき正義を訴えようとするものではない。むしろ、ユダヤ人であるかパレスチナ人であるかにかかわらず、そのような矛盾の中に置かれている人びとが、否めない非対称性の中で、複雑な葛藤を抱えながらどのようにして生きているのかを、なるべく判断や評価をまじえずに描こうとしている。かたく踏み固められた「正義」に依るのではなく、日々揺れ動く思いや行動を、距離を置いた静かな視点からそのまま見つめようとしている点において、本書はエルサレムを扱ったノンフィクションの中でも際だっている。
人びとが宗教的・政治的アイデンティティーだけで規定される存在ではないことは、無人地帯をはさんで、ぎこちなく挨拶を交わしたイラン系ユダヤ人のマヤと、アラブ人のアブドゥラ・バズラミトの微笑ましいエピソードや、鉄条網が撤去された後、通りをはさんで住んでいるイラン系ユダヤ人のマフソミ家とアラブ系ムスリムのヤグモア家との交流などからもうかがえる。アラビア語とヘブライ語の交換教授をしたり、ユダヤ教における食物の清浄規定(コーシャ)について対話を交わしたりする中で、物理的な境界や差別的制度の壁によって心の中に築かれた猜疑心の壁が徐々に崩れていく様子は希望を感じさせる。
しかし、同じマフソミ家の子どもたちも大人になると、娘のリヴカのように「ユダヤ人とアラブ人は平等に扱われている」と見る者もいれば、ピニのようにアラブ人に同情的で「自分がアラブ人だったらこんな差別はけっして受け入れられない」という者もいる。妹のリオラのように、この土地は私たちのものでアラブ人には渡すわけにはいかないと主張する者もいる。個人的な経験や暮らす環境のちがいによって、その見方は大きく変わる。
たしかにいえることは、分断や隔離を進めれば進めるほど、対話の機会は失われ、互いについての恐怖や猜疑心は増していくということだ。恐怖や猜疑心が高じるほどに、双方にとって相手は理解不能な怪物のイメージに近づいていく。一人ひとりの人間のちがいが置き去りにされ、「アラブ人はテロリストだ」「ユダヤ人はレイシストだ」といったステレオタイプ化した発言が一人歩きして、その追いつめられた行き先は暴力へとつながっていく。
ノーベル経済学賞を受賞したインドの経済学者アマルティア・センは、単一のアイデンティティーへのこだわりが暴力につながると指摘する。アイデンティティーとは他者や社会によって規定される自己のよりどころであり、具体的には国籍や宗教や民族、性別、政治的立場、職業など、特定の集団や信条への帰属意識だ。
特定のアイデンティティーへの帰属は、母体集団の結束力や構成員の自覚を促すが、行きすぎれば自分も集団も硬直化する。アイデンティティーを強固なものにするために、他者に対して排他的・暴力的になっていく。イスラエル・パレスチナで起こっているのは、まさにそういうことだ。イスラエルはユダヤ人国家であるという理念が根底にあるかぎり、「イスラエル」という仕組みは、曖昧なアイデンティティーに対して厳しい猜疑と警戒の目を向けつづけざるをえない。本書に登場するアラブ系イスラエル人のカレドはそんな状況を「みんな自分の嘘に守られて生きている」と表現する。
アイデンティティーに縛られずに、さまざまな矛盾に満ちた現実に対峙していくことはできるのだろうか。そのひとつの答えは、月並みではあるがやはり「対話」だろう。
本書の中で、1948年の第一次中東戦争のとき、イスラエル兵士たちがアブトルの丘に暮らす一人の哲学者を見つけたエピソードがちらりと紹介されている。ユダヤ人哲学者マルティン・ブーバーである。ブーバーはユダヤ人のパレスチナへの帰還には賛成していたが、ユダヤ国家の樹立には反対し、アラブ人との共存の可能性を唱えつづけた人物だ。ちなみに、ブーバーはその後アブトルから西エルサレムのタルビエの家に引っ越した。そこはパレスチナ人学者エドワード・サイードが生まれた家でもあった。
ブーバーの思想は、まさに「対話の哲学」である。ブーバーによると、現代社会では人と人の関係は「我ーそれ」の関係になってしまった。「我ーそれ」とは相手を自分のために利用する手段と見なす関係である。相手は「我」に従属している。これに対して「我ー汝」の関係では、互いに相手は独自性を保った他者であり、なにものにも従属しない。「対話」とはこの関係を保ちながら、共感を育てていくことである。西洋思想がモノローグにもとづいた哲学であったのに対して、近代のユダヤ人学者たちが自分たちの宗教的伝統や言語思想から生み出したのが「対話」(ダイアローグ)の思想であった。しかし、そうした思想的素地があるにもかかわらず、ユダヤ人国家を標榜するイスラエルにおいて対話が成立していないのは皮肉である。
本書の舞台となっているアサエル通りを歩いてみた。といっても、グーグル・マップのストリートビュー上での話だ。幅4メートルほどの石畳の道にはところどころ車が駐まっている。淡く赤みを帯びた石灰岩の壁で仕切られた西側には瀟洒な高級住宅がならび、ブーゲンビリアの深紅の花が咲きほこっている。東側はすこし低くなっていて、家々の屋上の貯水タンクやパラボラアンテナなどが見渡せる。南側の通りの入り口近くの西側の邸宅の壁に、アラビア語の落書きが見られる。本書にも登場するバズラミト家のザカリア夫妻のメッカ巡礼を祝うメッセージだ。向かいの家の壁にも漆喰の上に同様のメッセージやメッカのカアバ神殿やエルサレムの岩のドームの絵が描かれている。そこを通り過ぎて少し行くと、東側の家並みが切れて斜面の向こうに糸杉やアブトルの丘がのぞまれ、やがてまもなく通りは行き止まりになっている。
なんの変哲もない300メートルほどの道だが、半世紀以上にわたってここでくりひろげられてきたのは、まぎれもなく対話だったのだと本書を読んで思う。それは自分の内面に築かれた壁を崩して、相手の声に耳をかたむけるということだけを意味しない。むしろ、たいていの人は自分の中に壁が築かれていること自体に気づいていない。他者との対話を通してしか、人は自分の中にある壁に気づくことができない。街のそこここで、レイヤーの異なる世界に暮らす人たち同士の間で、このような対話は人知れずくり返されてきたにちがいない。しかし、分離壁のような分断政策は、そうした草の根の対話の可能性すら奪うことになる。そのような「対話の空間」を、これから、どこに、どのようにつくっていけるのだろう。
著者略歴・訳者略歴
<著者略歴>
ディーオン ニッセンバウム(Dion Nissenbaum)
米紙ウォールストリート・ジャーナル記者、国家安全保障担当。中東や南アジアの紛争地帯を数多く取材し、アフガニスタンでは主任特派員として各地の戦場や村に入り、時には米軍と行動を共にした。エルサレムには4年間駐在し、かつて東西エルサレムを分かっていたアブトルに住んだ。全米記者クラブ賞などを受賞。
<訳者略歴>
沢田博(Hiroshi Sawada)
1952年東京都生まれ。「ニューズウィーク日本版」編集顧問。「図書新聞」、「ニューズウィーク日本版」、「エスクァイア日本版」の各編集長を歴任。編著書に『「ニューズウィーク」で読む日本経済』、『ジャーナリズム翻訳入門』など。訳書に、タリーズ『名もなき人々の街』『有名と無名』、グッドソン『アフガニスタン 終わりなき争乱の国』ほか多数。